 シュヴァルツの手記の写本のうち、198頁から成るエルビンク版(1551)
で、第2手記本文は先の秘密帳の195頁で終っている。続く 196〜197頁には次のような記入が見
開きである。手記の構成を検討した際、第2手記「後記」と呼んだ部分である。
シュヴァルツの手記の写本のうち、198頁から成るエルビンク版(1551)
で、第2手記本文は先の秘密帳の195頁で終っている。続く 196〜197頁には次のような記入が見
開きである。手記の構成を検討した際、第2手記「後記」と呼んだ部分である。
 シュヴァルツの手記の写本のうち、198頁から成るエルビンク版(1551)
で、第2手記本文は先の秘密帳の195頁で終っている。続く 196〜197頁には次のような記入が見
開きである。手記の構成を検討した際、第2手記「後記」と呼んだ部分である。
シュヴァルツの手記の写本のうち、198頁から成るエルビンク版(1551)
で、第2手記本文は先の秘密帳の195頁で終っている。続く 196〜197頁には次のような記入が見
開きである。手記の構成を検討した際、第2手記「後記」と呼んだ部分である。
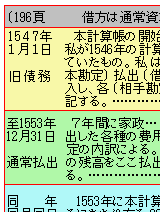
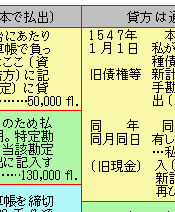
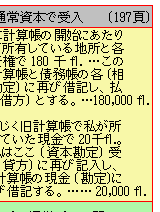
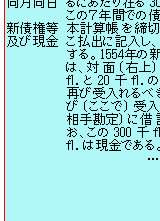
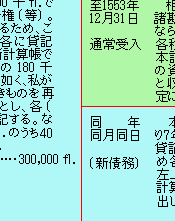
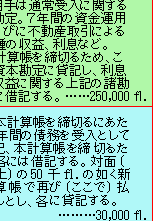
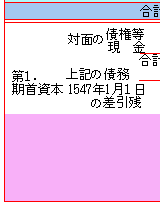
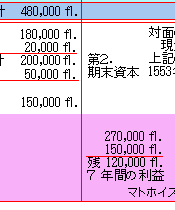
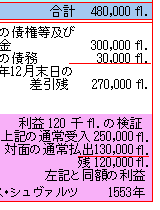
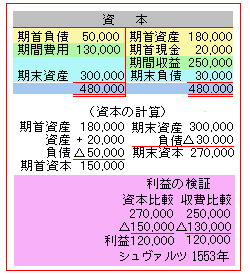
 この見開きの2頁には、
「計算帳の開始と締切の仕方および利益の計算と照合の仕方(Wie mann ain rechnung
anfahen, beschliessen vnd den gewin suechen vnnd machen solle)」と見出しは付
けられているが、特に内容について解説の類は付されていない。
この見開きの2頁には、
「計算帳の開始と締切の仕方および利益の計算と照合の仕方(Wie mann ain rechnung
anfahen, beschliessen vnd den gewin suechen vnnd machen solle)」と見出しは付
けられているが、特に内容について解説の類は付されていない。
 その内容は左図のように要約できる。
その内容は左図のように要約できる。
 上部は「通常資本(capital jeneral)」勘定である。そこで
の記入は、各関連勘定を相手に、期首と期末の2回に分けて、行われたものと考えら
れる。即ち、先ずは1547年1月1日の開始記入で、期首の資産と負債が記入される。
次は1553年12月31日の締切記入で、当該期間の受払および期末の資産と負債が記入さ
れる。これらが見出し前半の「計算帳の開始と締切の仕方…」に相当する部分である。
なお、備考欄によれば、翌期首には当期首と同一の記入がなされる。
上部は「通常資本(capital jeneral)」勘定である。そこで
の記入は、各関連勘定を相手に、期首と期末の2回に分けて、行われたものと考えら
れる。即ち、先ずは1547年1月1日の開始記入で、期首の資産と負債が記入される。
次は1553年12月31日の締切記入で、当該期間の受払および期末の資産と負債が記入さ
れる。これらが見出し前半の「計算帳の開始と締切の仕方…」に相当する部分である。
なお、備考欄によれば、翌期首には当期首と同一の記入がなされる。
 見開き頁の下部では、資産から負債を控除する形で、期首(見開
き左頁)と期末(同右頁)の資本を算出している。そして、最下部で「利益の検証(Proba
der 120 M fl. gwin)」と称し、これらの資本比較と収費比較による利益を照合している。
見出し後半の「…利益の計算と照合の仕方」に相当する部分である。
見開き頁の下部では、資産から負債を控除する形で、期首(見開
き左頁)と期末(同右頁)の資本を算出している。そして、最下部で「利益の検証(Proba
der 120 M fl. gwin)」と称し、これらの資本比較と収費比較による利益を照合している。
見出し後半の「…利益の計算と照合の仕方」に相当する部分である。
 以上の構成から、内容的に、この見開きの2頁は、第1手記の「3種の簿記」にも、
第2手記の「秘密帳簿記」にも関係なく、全く独立したものといえる。
以上の構成から、内容的に、この見開きの2頁は、第1手記の「3種の簿記」にも、
第2手記の「秘密帳簿記」にも関係なく、全く独立したものといえる。
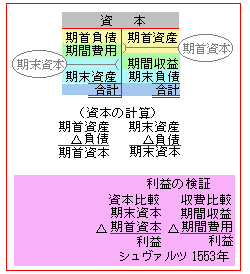
 上図の内容は更に左図のように要約できる。
上図の内容は更に左図のように要約できる。
 上部の「通常」資本勘定では、
開始記入で期首の資産と負債が記入される結果、貸方残高が期首資本を示すことになる。また、
締切記入では、当該期間の受払(収費)が振り返られた段階で、貸方残高は期末資本を表すが、
更に期末の資産と負債が振替えられることにより貸借合計は一致し、繰越試算表的役割を果た
すことになる。
上部の「通常」資本勘定では、
開始記入で期首の資産と負債が記入される結果、貸方残高が期首資本を示すことになる。また、
締切記入では、当該期間の受払(収費)が振り返られた段階で、貸方残高は期末資本を表すが、
更に期末の資産と負債が振替えられることにより貸借合計は一致し、繰越試算表的役割を果た
すことになる。
 その様式が第2手記の債務帳にある「資本(Haubt)」勘定(債丁7)
1)と秘密帳にある
「総資本(Cauedal general)」勘定(秘丁16)2)
に似ているところをみると、両勘定を「通常資本(capital jeneral)」勘定として一般化し、その決算処理を
一般的に示したものかもしれない。但し、こうした「開始と締切の仕方」は既に第1手記(1518)においてみら
れたものである。
その様式が第2手記の債務帳にある「資本(Haubt)」勘定(債丁7)
1)と秘密帳にある
「総資本(Cauedal general)」勘定(秘丁16)2)
に似ているところをみると、両勘定を「通常資本(capital jeneral)」勘定として一般化し、その決算処理を
一般的に示したものかもしれない。但し、こうした「開始と締切の仕方」は既に第1手記(1518)においてみら
れたものである。
 上部の資本勘定では、期首も期末も資本の金額そのものは
算出・表示されていない。それは下部で資産から負債を控除する形で行われているが、そこで
算出された数字は、最下部で行われる「利益の検証」に用いられている。そこでの「利益の
計算と照合の仕方」は、いわゆる損益法と財産法によるものであるが、ドイツ最初の簿記書
であるグラマトイス(1521)以来、ドイツ簿記書史においては既にみられたものであった。
上部の資本勘定では、期首も期末も資本の金額そのものは
算出・表示されていない。それは下部で資産から負債を控除する形で行われているが、そこで
算出された数字は、最下部で行われる「利益の検証」に用いられている。そこでの「利益の
計算と照合の仕方」は、いわゆる損益法と財産法によるものであるが、ドイツ最初の簿記書
であるグラマトイス(1521)以来、ドイツ簿記書史においては既にみられたものであった。
 1547年1月1日の開始記入の前日と、1553年12月31日の締切記入日に、
シュヴァルツの勤務していたフッガー家で大決算が行われているが
3))、
この見開き2頁にわたる内容は、その結果に直接関係していない。
日付のみ参照し、決算処理を一般的に示したものであろう。
1547年1月1日の開始記入の前日と、1553年12月31日の締切記入日に、
シュヴァルツの勤務していたフッガー家で大決算が行われているが
3))、
この見開き2頁にわたる内容は、その結果に直接関係していない。
日付のみ参照し、決算処理を一般的に示したものであろう。
 見開き2頁の下部、「利益の計算と照合の仕方」の最下行には、上掲の要約図にも示したように、
シュヴァルツの名前が記されている。
見開き2頁の下部、「利益の計算と照合の仕方」の最下行には、上掲の要約図にも示したように、
シュヴァルツの名前が記されている。
 エルビンク版(ヴァイトナオエル翻刻)では、名前の後に1553年の年数も記入されて
いた。エルビンク版の本文は1551年に完成しているので、この1553年は、見
開き頁が写本の本文完成後に追記されたことを意味するものであろう。
エルビンク版(ヴァイトナオエル翻刻)では、名前の後に1553年の年数も記入されて
いた。エルビンク版の本文は1551年に完成しているので、この1553年は、見
開き頁が写本の本文完成後に追記されたことを意味するものであろう。
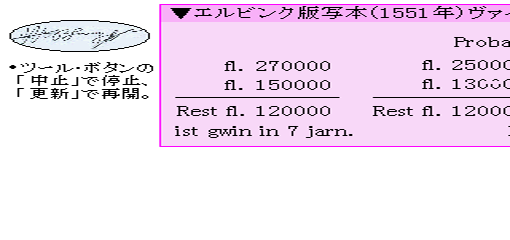
 ウィーン版(1555年)では、この部分にシュヴァルツの名前のみがある。この署名
につき、ヴァイトナオエルは注4)
で「その筆跡は全体に丸みを帯びている。恐ら
く原本にあったシュヴァルツのサインを真似したものであろう」と推測している。
ウィーン版(1555年)では、この部分にシュヴァルツの名前のみがある。この署名
につき、ヴァイトナオエルは注4)
で「その筆跡は全体に丸みを帯びている。恐ら
く原本にあったシュヴァルツのサインを真似したものであろう」と推測している。
 グダニスク版(1564年)には、エルビンク版と同じくシュヴァルツの名前と1553
年の年数が記されている。筆跡は見開き2頁のものに酷似しているので、写本作成者によるものと
思われる。なお、このグダニスク版にのみ、最下行に見開きの両頁にわたり2行で「秘密混合簿記の終り
(Endt der Gehaim, Gehaimnwex., vermischtens buchhaltens)」と記されている。見開きのこの2頁が
秘密帳に続いていたため、写本作成者がその内容を吟味することなく、秘密帳簿記の最後部と誤解し記
したものであろう。
グダニスク版(1564年)には、エルビンク版と同じくシュヴァルツの名前と1553
年の年数が記されている。筆跡は見開き2頁のものに酷似しているので、写本作成者によるものと
思われる。なお、このグダニスク版にのみ、最下行に見開きの両頁にわたり2行で「秘密混合簿記の終り
(Endt der Gehaim, Gehaimnwex., vermischtens buchhaltens)」と記されている。見開きのこの2頁が
秘密帳に続いていたため、写本作成者がその内容を吟味することなく、秘密帳簿記の最後部と誤解し記
したものであろう。
 シュヴァルツはこの手記を「青
春の想い出として書いた」と述ベていた。しか
し、「この業績を主人のヤコブ・フッガーが同家の費
用で活字にしてくれるよう期待した
7)」との説があ
るように、手記の主要部分の「例示」は全体としてフッガー家
の内容に依り過ぎ、一般的性格を欠くきらいがあった。 シュヴァルツはこの手記を「青
春の想い出として書いた」と述ベていた。しか
し、「この業績を主人のヤコブ・フッガーが同家の費
用で活字にしてくれるよう期待した
7)」との説があ
るように、手記の主要部分の「例示」は全体としてフッガー家
の内容に依り過ぎ、一般的性格を欠くきらいがあった。
|
 第4章第5節の終り
第4章第5節の終り
(先へ進む)